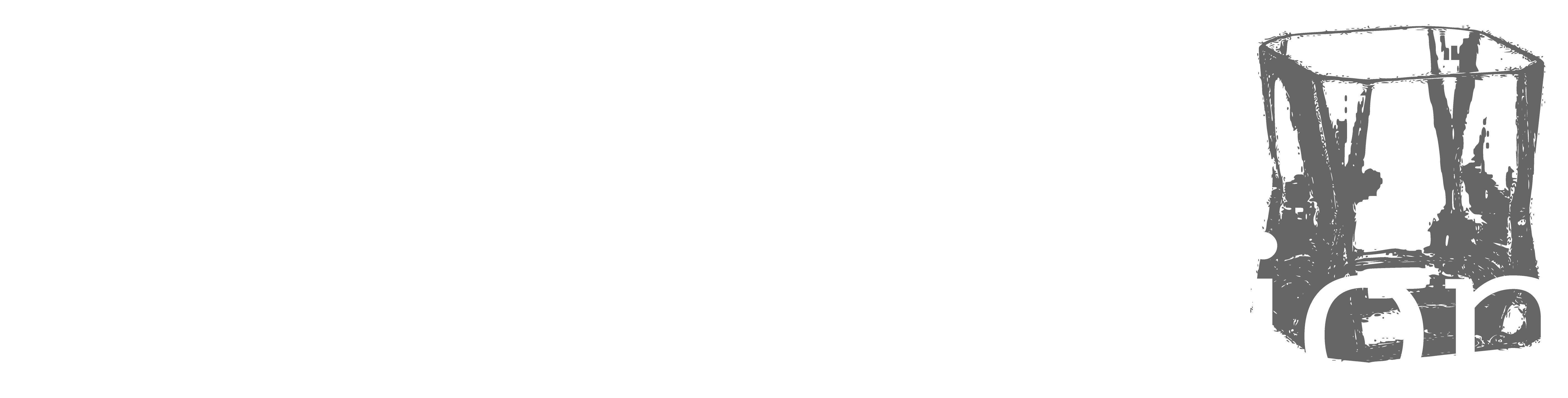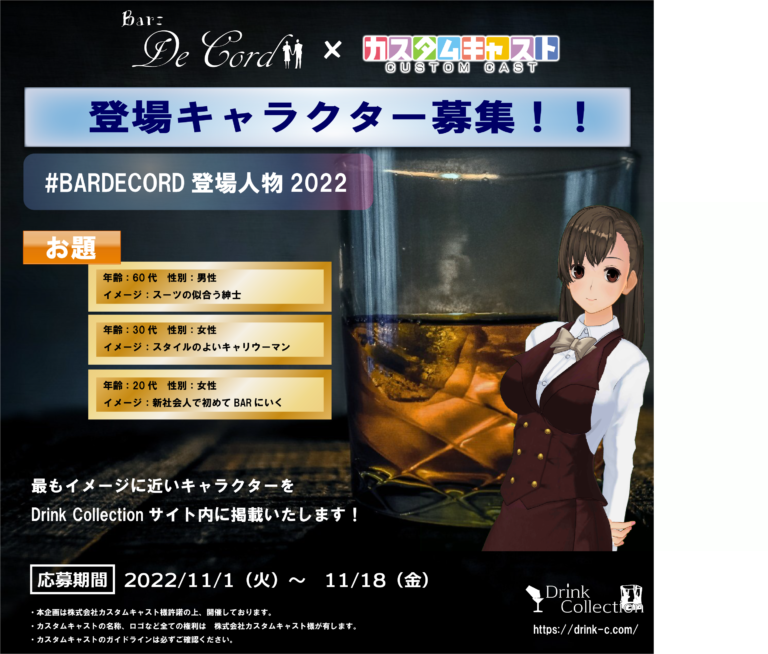Table of Contents
introduction
今回はカクテルコンペティションについて解説してみようと思います。
コロナ禍で開催自体は減っていたかもしれませんが、今後は新たな大会なども開催されるかもしれません。
通っているバーのバーテンダーが出場していたりすると、そのような催しがあることは認識されている方もおられると思いますが実際に観戦されたことがない方のためにどのようなものか自身の経験も交えてお話しします。
カクテルコンペティションとは
簡単な話ですがカクテルの大会です。
少し大雑把な説明すぎますが、エントリーしたバーテンダーの方々がそれぞれその日のために試行錯誤を重ねて作り上げたカクテルを披露する場となります。
大会によっては指定されたスタンダードカクテルを作ることもありますが今回はオリジナルカクテルでのカクテルコンペティションについて触れたいと思います。
オリジナルカクテルとは言え、大抵の大会では酒類メーカー側から指定のアイテムを使用するかそのメーカーの取り扱い商品を使用する必要があります。
個人的にはアイテムが指定されている方がカクテルを考えやすく感じます。
指定アイテムがある場合はそれ自体が持つストーリーや背景をイメージしたり単純に味覚的相性でレシピを考えたりもしますが、指定がない場合は無限に近い選択肢から材料を選ぶひつようがあり途中まで考えたレシピを全てリセットしたりとなかなかに骨が折れます。
しかしながら数多の材料を扱いカクテルを作っていく経験はバーテンダーとしての大きな糧となります、少しでも興味があるバーテンダーの方には是非挑戦していただきたいものです。
採点に関して
どうしても応援しているバーテンダーがよく見えてしまいますが、実際の審査や採点はそれだけでは決まりません。
審査や採点の項目は大会によって違いますが、優れていた点を評価する場合と減点方式での採点と大きく2つのパターンが多いと思われます。
加点方式であれば良いですが、減点方式の場合は服装や髪型なども含まれることが多いです。
印象という何とも基準がない部分まで採点項目に入ることもあるので、過去の入賞者や先輩バーテンダーからのアドバイスが必須になることもあります。
経験上素晴らしいカクテルさえ作れば良いとは言えないと思います。
もし何らかの大会に出場が決まったなら、過去に同じ大会に出場された方にアドバイスを求めるのが最善の手かもしれません。
大会へのエントリー方法
出場するためのエントリー方法も大会によって様々です。
エントリー用紙を記入し提出するだけで出場できる大会もあるにはありますが。メーカー主催の場合はインターネットを用いたエントリーであったり、大会開催までにSNSを使ったプロモーションが必要だったりと多数の方法があります。
気づいた時にはエントリー期間が終了していることもあるのでSNSなどでまめにチェックしておきましょう。
バーテンダー協会などに所属していれば開催などの情報は入手しやすいかも知れません。
Ending
カクテルコンペティションはそれ自体も見ていて楽しめる良いイベントではありますが、規模によっては各酒類メーカーのブースが出ていたりするので新たなお酒やカクテルに出会える場所でもあります。
出場するバーテンダーにとっても素晴らしい経験となる場でもあるので、馴染みのバーテンダーが出場すると耳にされたら是非会場へ足を運ばれることをお勧めします。